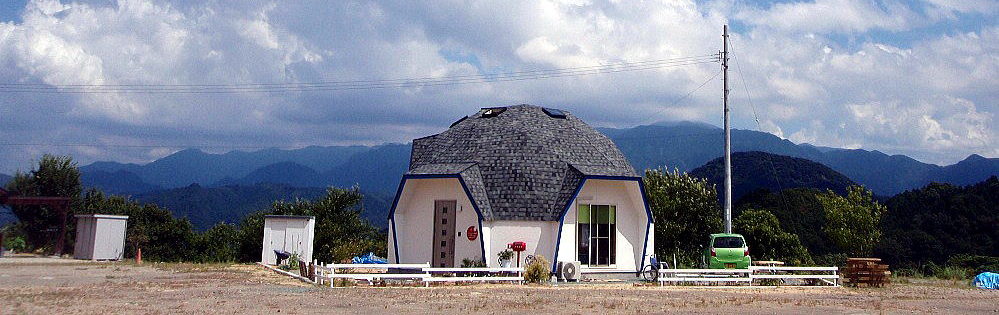2014年7月24日
はい、どっとちゅーんあっぷ(=^o^=)やまねこ拝でございます。
今回、ミヒャエル・デーブス先生を迎え四国アントロポゾフィー・クライス主催での夏の講座を 松山で催し、無事完了いたしました。
ミヒャエル・デーブスさんの講演『意識魂の時代の幕開けに 於ける薔薇十字会の衝動』についてのレポートです。 竹下さんの通訳で、やまねこが理解できた部分についてのみ書いてみますが、なんとも深く広がり のあるデーブスさんの司祭さんとしての霊性については表現が及ばないかもしれません。
講義はまず、「眠っている人間はどこにいますか?」というデーブスさんの質問から始まります。 考えることに誘う・・・独特の語り方です。
肉体は横たわり、呼吸はしているが意識はない人間とは・・眠っている。
そこには肉体とエーテル体があり、意識の本体としてのアストラル体は自我(わたし)とともに 宇宙に回帰している。
これは良く知られたシュタイナーの「神秘学概論」や「神智学」に語られる 霊学的人間像です。
デープスさんの語り方がわたしたちを、引き込んでゆくのはあたかも 「解き明かす」ように質問しながら「思考にいざなう」というというスタイルです。 あるいは「ツルの折り紙」の折り方を教える先生のようでもあります。出来上がった折り紙を 示しながら、もう一度一枚の折り紙に展開してゆくような語り口は、とても東洋的とも言えます。
それから、おもろむろにエーテル体とはアストラル体にとって「鏡」の役割をしている。 エーテル体と結びつくことで現実の世界に目覚めることができる。エーテル体を離れると意識は なくなるが、本当は宇宙にいるアストラル体と自我は目覚めている。
それを認識するのは、死の直後エーテル体とアストラル体のみに分離したとき。この強烈な目覚め が続くのは三日間くらい。エーテル体は崩壊して再び意識を失う。そして徐々に意識を回復するが 「燃えるような体験・痛み」を通して人は「本質的なことと非本質的なことを分離してゆく」 この世界を東洋ではカーマ・ローカ(欲界)という。キリスト教のカトリックでは煉獄とも言う。 最初のレクチュアだけでもこんな感じです。
そして講演のメインの薔薇十字と個性(インディビジュアリティ)と人格(パーソナリティ)の問題 に深く触れてゆきます。
転生における「不死の自我」としての「個性」、現世的な「人格」は 地上的な事にのみ関わり、古代の秘儀においては不死の個性にウェイトが置かれていた。
このことをマイスター・エックハルトは「自分が王様であることを知らなかった男の物語」 で語っている。
しかし、キリストが地上に受肉したことによって「人格」が不死になることが可能になった。 ゆえに秘儀参入者の役割はキリスト以前と以後では変化してゆく流れがある。
中世から近代にいたるプロセスは、キリストの霊的な働きの元に「人格」の不死化・・・つまり 感覚的・物質的な世界にもっとも高い神性が降りてくる時代が始まった。 その萌芽は十三世紀という今だ近代とは呼ばれていない「中世」に淵源する。
この流れをクリスチャン・ローゼンクロイツとヨーロッパでは呼ばれている。
徒弟・職人・マイスターという生き方と秘儀の伝授のあり方は古代のフリーメーソンにも 語られている。
そして中世的世界観では太陽系は天動説のもとにあった。 中世ヨーロッパでは古代ギリシャの宇宙観にもとづいて、地球は静止した固い球体で 入れ子式の透明な七つの球体に包まれた中心にあると考えられ、この七つの天球はそれぞれ回転して いてひとつの天球には惑星が宿っているされ、それは月・水星・金星・太陽・火星・木星・土星 であり、一週間の曜日にあたります。 そして、七つの天球が発する音は「天球の音楽」という音階を構成しており、同時に七つの金属 ・・・銀(月) 水銀(水星) 銅(金星) 金(太陽) 鉄(火星) 錫(木星) 鉛(土星)に対応している という。そして人間は天界から地上に下るときにこの七つの天球を旅してこれらの金属の性質を 帯びるということらしい。デーブスさんは人間が展開から地上に降りてくるときに「火星領域」 を最後に通り、そこに「地上的課題」(転生のテーマ)を受け取るのだと言います。
しかし、火星は鉄の惑星であり、争い・戦いの星である火星は、人間のエゴイズム・唯物論にも 関わっている。
かつて象徴的な会議が天界で催された。(これは神話的メタファーと受け取ってくださいと ことわりつつ)マニとスティキアノスとブッダとゾロアスター、そしてローゼンクロイツ が地球の未来について話し合った。 人間は神々の世界を離れてゆくごとに物質化し、感覚的になり、霊性を失い争いの性質を帯びる ようになり、古代の霊性は失われてゆく・・・そこでブッダは火星領域に赴いて平和のエネルギー を注ぎ込み、キリストの地上への受肉に関わることにした。 聖歌『天のいと高きところに神の栄光あれ、地には善意の人に平和あれ』の平和の人とはブッダ のことである。そして、ローゼンクロイツは「キリストの自我」の使命、人格の不死化に関わる。 中世の神学、とりわけトマス・アクィナスは、近代の発端となる「思考を通した霊性の目覚め」 を担っている。
後世のマイスター・エックハルトやニコラウス・クザーヌスにいたるドイツ神秘主義 の精神史は「近代の基盤」とも言える。
古代の秘儀参入者は、アトランティスの叡智を携えてまずチベット山脈に逃れた。 海底に沈んだアトランティス秘儀参入者の代表はマヌであり、チベットから川沿いに叡智が下り やがで古インド文化となった。そしてシュメール・カルデア、エジプト、ギシリャ・ローマの第四 文化期へと移行する。アトランティスの叡智は西へと伝波して西洋・近代にいたる時代に 後アトランティス第五文化期が十五世紀にはじまる。 ルネサンス・宗教改革・哲学・自然科学にはじまるわたしたちかよくしる「近代」です。
デーブスさんのレクチャーは、西洋の中世・近代史の深い地下水脈とも言える精神史を解き明かして ゆきます。そして薔薇十字こそがその精神的な衝動の根底にあるというのです。
そして、神秘学では近代のはじまりは1614年薔薇十字友愛宣言からと言われています。 一般の西洋史でもデカルトが登場する時代ですから近代そのものです。 薔薇十字団は伝説としては以下のように語られています。
「1614年、ドイツのカッセルで「称賛すべき薔薇十字団の名声」が出版されます。続いて、 「友愛団の告白」「クリスティアン・ローゼンクロイツの化学の結婚」が出版され、多くの人々が 運動を誉め称える本を書いたり、また、認められて加入できることを期待したり、あるいは異端で あるとして攻撃するなど、これらはドイツで大きな反響を巻き起こします。しかし、その実体が 明かされることはありませんでした。 薔薇十字団とは何なのか?出版された文書によると、クリスティアン・ローゼンクロイツと いう人物が中東を旅行して神秘学の知識に通じ、ドイツに帰り秘密の友愛団を結成した後、百六歳 まで生き、埋葬され百二十年後に彼の納骨堂が薔薇十字団員によって発見され、それが合図となって 友愛団は自らの存在を公表し、ヨーロッパの智者たちに参加を呼びかけました。薔薇十字団員は、 社会を奇跡的に変革して新時代を到来させる秘密の知恵の鍵を所有しているとされています。 多くの人が入団の意思を示したが、どうやら薔薇十字友愛団から返答を得た者はいない。 返答する意思が無いのに、なぜ彼らは参加を呼びかけたのか。 出版された文書の著者は何者なのか。ヨーハン・ヴァレンティン・アンドレーエ(1586-1654)が 薔薇十字伝説の創始者かどうかはわからないが深く関わっていた。しかし、アンドレーエが果たし た役割に関してはわかっていない・・・。
(薔薇十字団について) 様々な寓話と象徴とと混沌に満ちている薔薇十字団の伝説と「噂」は、ひとつのトレンドを 醸し出しやがて、近代の誕生となります。
デカルト、ライプニッツ、ニュートン、ロバート・フラッドなどなど薔薇十字団に関わったとされる 数学者・科学者・哲学者は数多く、この秘密結社がヨーロッパの深層の歴史と関わっていたことは、 疑い得ないにしてもその実態はやはりすべては謎として残されたままです。」
また、講座の後半の質問時間にはデーブスさんは「アジア人と古代の霊性」「日本人の課題」など 興味深いお話をされました。同じアジアでも中国は大陸系の文化もコリアは半島系、日本は島国 の文化で体質は微妙に違うのだそうです。また第五文化期は同時代性の強い時代なので世界各地の 地域性よりも人間の普遍性に重きがあるのだそうです。 西洋、東洋と分けすぎる必要は薄れているとも。
また「わたしたち日本人の現代の課題はなんですか?」との質問に 「日常の小さな不安を克服する力を養うこと」と語られました。
ドイツとアジアを両面から見ているデーブスさんはこの度の東日本大震災で見せた日本人の粘り強さ や底力、火事場の馬鹿力に驚嘆する一方で、平時に細やかで繊細で時には些細なことで不安を 抱きやすいナイーブさを併せ持っているメンタリティに注目している様子。 一端ことが起きたら「腹がすわって大胆になる」一方で小さなことでくよくよする日本人と言うのも 当たっているかなと思いました。
竹下さんによればそんなテーブスさん自身もきわめて頑固で論理的で「自分のポリシーは何が あっても曲げない」というどんなドイツ人よりもドイツ的なのだと言います。
しかし、その語り口は、徹頭徹尾熱っぽく、オブシェクティブかつ東洋的でドイツなんだか日本人 なんだかわからないという不思議な魅力がありました。 ひとつひとつ風呂敷包みをていねいに開いてゆくような礼儀正しい人あたりは日本のどこでも 通用しそうでした。
やまねこ本人にとっても四国アントロポゾフィー・クライスの過去の公開講座を総括するような 印象深い薔薇十字とルドルフ・シュタイナーの深い謎に触れる松山講座でありました。
※ここにレポートできたのはわたしが理解できたレクチャーのごく一部であることを
重ねてお断りしておきます。